「共感覚者の驚くべき日常」という書籍に、「味に形を感じたり」「音を聴くと色光が見える」といった共感覚者についての研究があります。
これは、「活動的で火のような音楽」といった、私達が言葉によって表現する印象や比喩とは全く別のもの。
実際に光や色彩の塊が目の前に現れ、外から受ける刺激と同様の感覚が再起される人たちについての記述です。
これまで非科学的だという理由から、ほとんど研究されなかったテーマだとのことです。
この本は、「客観的に証明できるもの」だけを『科学的』と呼ぶ従来のものの見方にも疑問を投げかけていて、「主観的な経験や、直観的に理解していること」を丁寧に扱うことが、このような現象の本質に近づくためには必要との立場をとります。
この態度は、現代のテクノロジーや科学観が抱える矛盾や問題を克服するための指針としても重要で、とても面白い本だと思いました。
また、これらの現象にインスピレーションを受けた創作活動として、興味深いものが多数記載されていたので、これらの例を参考までに挙げておきます。
(実際の共感覚体験と、意図的に音と色彩を共通のテーマとした創作とは、混同してはならないと強調されていることには注意が必要)
■自然科学的な主題としての関心からの取り組み
1704年、アイザック・ニュートンが音波の振動数とそれに対応する光の波長を等しくする数式を組み立てようとして苦心した。
1725年、視覚クラブサンという音と光で奏でる楽器が登場した。同様の装置はたくさんつくられている。
1810年、ゲーテが、「色彩論」で色覚とそのほかの感覚との対応について詳しく述べる。
■共感覚をもっていた芸術家による作品
1915年、作曲家スクリャービンが交響曲「プロメテウス」で、自身の共感覚を表現しようと試みる。色光をコントロールするキーボードや、光線をコンサートホールに放つなど。当時の技術では限定的な再現しかできず。
共感覚のある画家、カンディンスキーは、「コンポジション」「即興」と名づけた絵画で、音と色の調和関係を表現。
【関連】
「共感覚者の驚くべき日常」を書評しているページ
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/000533.html



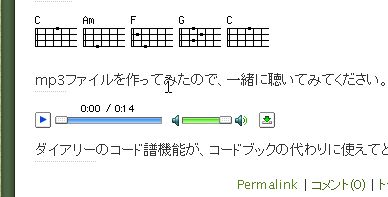

最近のコメント